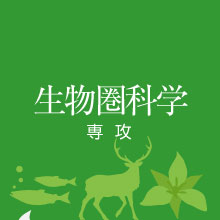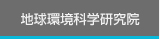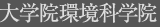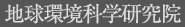水圏生物学コース

水圏生物学コースでは、地球の70%を占める水圏環境、すなわち淡水生態系(河川・湖沼・湿原)と海洋生態系(沿岸・外洋)に生育する生物群を対象として、環境応答、環境適応、生物生産、多様性、モニタリングなどの解明を目的として遺伝子・細胞レベルから個体・群集レベルまで種々の手法を用いて研究を進めています。また、本コースの構成教員は北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーションに所属しているため、大学院での研究教育は個性と魅力あるフィールドを有する臨海実験所等で展開することになります。各実験所の活動はホームページ(http://www.hokudai.ac.jp/fsc/)を参照して下さい。

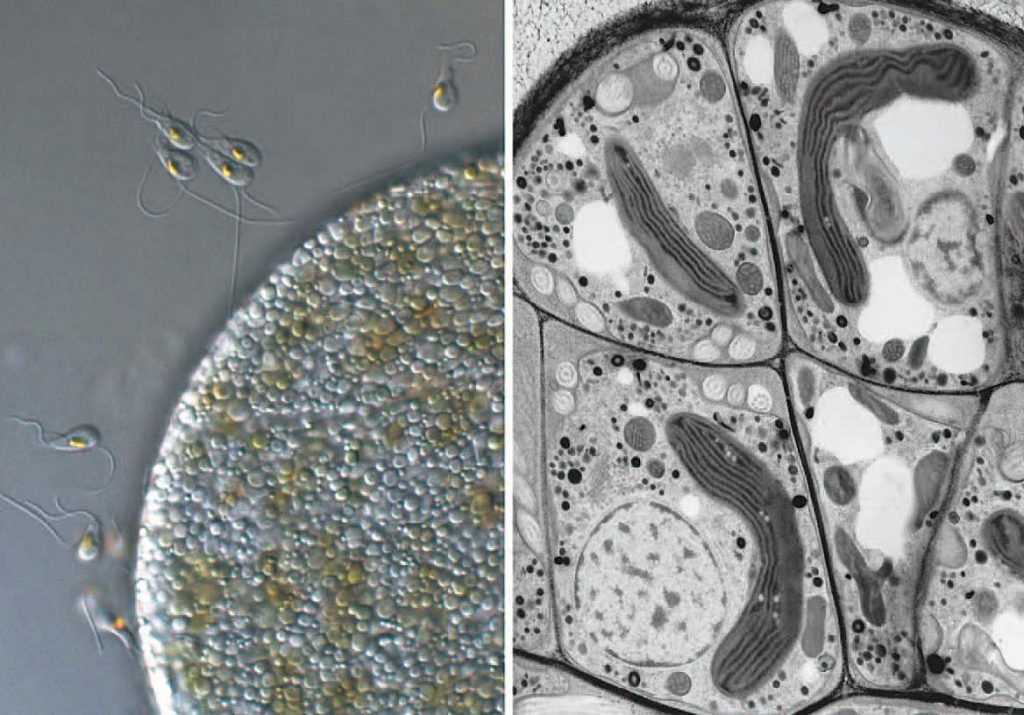




担当教員紹介
宮下 和士 教授
Kazushi Miyashita, Professor
水圏生物資源計測学、システム水産学
[生態系変動解析分野]
長里 千香子 教授
Chikako Nagasato, Professor
藻類学、細胞生物学
[室蘭臨海実験所]
仲岡 雅裕 教授
Masahiro Nakaoka, Professor
海洋生態学、群集生態学
[厚岸臨海実験所]
四ツ倉 典滋 教授
Norishige Yotsukura, Professor
海産植物学、多様性保全学
[忍路臨海実験所]
南 憲吏 准教授
Kenji Minami, Associate Professor
沿岸資源計測学、音響計測学
[生態系変動解析分野]
伊佐田 智規 准教授
Tomonori Isada, Associate Professor
生物海洋学、衛星海洋学
[厚岸臨海実験所]