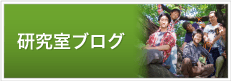2024年4月 15名
教員1名+博士課程8名+修士課程5名+研究生1名
准教授:小泉逸郎
D3+: 島本悠希、鈴木規慈(休学中)、中正大
D3:植村洋亮、今野友陽、勝島日向子
D2:賈煒(かい)
D1:三枝弘典
M2:布川里和、早川慧、吉野裕生
M1:遠藤岬、根来晃佑
研究生:千田晋
准教授
小泉 逸郎 / Itsuro Koizumi(個人ページ)
itsuro (at) ees.hokudai.ac.jp

フィールドベースの動物生態学
生態学の醍醐味と言えばフィールドで生き物達と向き合うこと。最近は昔ながらの泥臭いフィールドワークが減ってきている気がします。北大の、そして動物生態学コースの伝統であるパワーエコロジーを目指して楽しい研究をしましょう!
博士課程
博士3+年
島本 悠希 / Yuuki Shimamoto
Y.Shimamoto3091(at)ees.hokudai.ac.jp
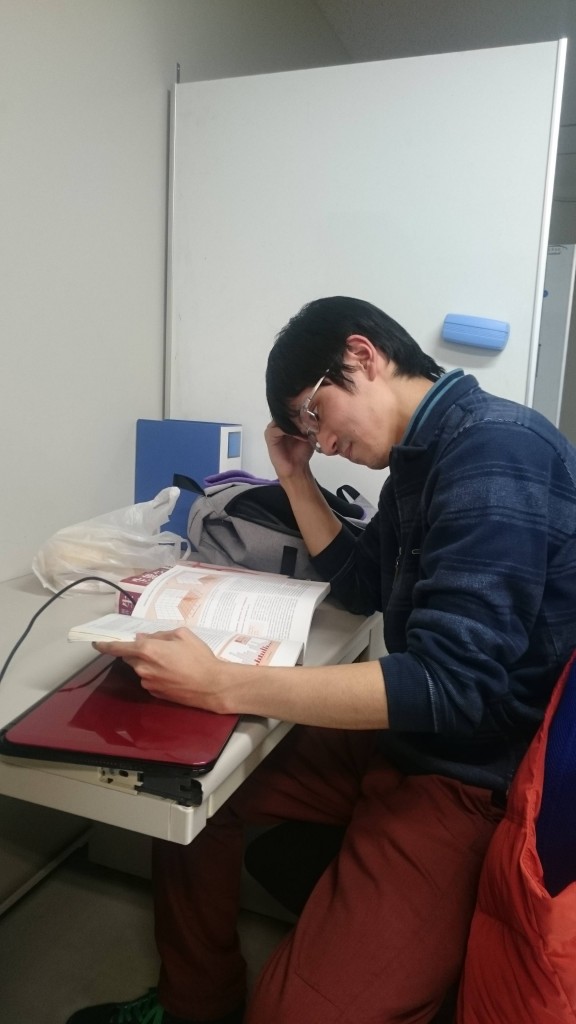
魚類の脳形態と認知能力への養殖の影響
生物は外界から情報を得て、適切に応答する能力を持っています。自身を取り巻く環境をうまく認知して、そこから得た情報を処理するのに重要な役割を果たしているのが「脳」です。脳のかたちは非常に多様化しています。分類群ごとに形態が異なるのはもちろん、同じ分類群内、たとえば魚類の中でも、住んでいる環境によって特徴的な進化を遂げています。
では、自然界とは大きく異なる環境で暮らす養殖魚たちの脳は、自然界で暮らす魚たちと比べて、どのように変化しているのでしょうか?私は、北海道に限らず全国で養殖されている、さまざまな魚種を対象に、脳の形態と認知能力に注目して研究を進めていきたいと思います。
鈴木 規慈 / Noriyasu Suzuki(社会人ドクター、休学中)
noriyasu_s_suzuki (at) eis.hokudai.ac.jp

カワバタモロコの保全生態学
北海道から遠く離れた滋賀県で、北海道には分布していないカワバタモロコという小さな魚の研究をしてきました。小さな魚の小さな魚なりの面白さと守るべき価値を学術的にまとめた上で、保全にもつなげていきたいと考えています。
中 正大 / Masahiro Naka
nakanakamonaka (at) ees.hokudai.ac.jp

魚類寄生虫群の形成要因
「どこのどんな魚に寄生虫が付いているのか、そしてその寄生虫はどうしてそこにいるのか」ということに興味を持っています。
寄生虫が宿主の魚と周囲の環境条件に影響されながら群集を形成しているようなので現在はそれを調べています。寄生虫の種同定も修行中です。はやく一人前になれるようにがんばります。
最近、プチ自分探しを始めました。
博士3年
植村 洋亮 / Yohsuke Uemura(学振特別研究員DC1)(個人ページ)
uemura.fish (at) gmail.com
気候変動にともなう河川性サケ科魚類の個体群動態予測
今野 友陽/ Tomoaki Konno (個人ページ)
ザリガニとその寄生虫の相互作用・共進化・系統地理
勝島 日向子/ Hinako Katsushima(学振特別研究員DC2) (個人ページ)
hinako.katsushima (at) gmail.com

森林に生息する哺乳類のにおいコミュニケーション
誰しも一度は「人間(自分)はなんで生きているのかな」って考えますよね。そんな途方もない疑問に、生物学の目線から自分なりの答えを見つけることが目標です。私たちはどうして生きているんだろう?どこまで自分で決めることができて、どこまで決められているのだろう? 野生動物の生きざまを調べながら、そんなことを考えたいです。
特に哺乳類のコミュニケーション・社会性の進化に興味があります。最近はヒグマの世界にお邪魔して研究しています。見て嗅いで触って食べて聴いて面白い研究ができるよう頑張ります。
野外風景と野生動物が大好きなので、2019年に中国から北海道に来ました。北大文学院で修士号を取得した後、小泉研に入りまして、新しい世界を開きました。。空気、ジンギスカン、インスタントラーメン、お水、北海道の全部がおいしいと思います。自分の研究対象ザリガニで、北海道でたくさん野外調査、ドライブをすることができて、本当に嬉しいです。現段階、たくさんの過去データを解析しています。統計がちょっと苦手なので、色々お話ししましょう。
博士1年
三枝 弘典/ Hironori Mieda
lutra-hironorius716(at)eis.hokudai.ac.jp
ヤツメウナギ類の繁殖生態
ローレンツ博士の『ソロモンの指輪』を中学生の時に読んでから、行動学に興味を持つようになりました。協力行動、社会行動、配偶行動・・・生き物の行動は不思議がいっぱいです。
そんな魅力的な生き物の行動の中でも、ヤツメウナギの配偶行動について研究する予定です。変態するヤツメウナギはシン・ゴジラを彷彿させます。
研究室のメンバーからたくさんの刺激を受けながら研究を楽しみたいです。
修士課程
修士2年
布川 里和 / Satowa Nunokawa
TBA(ヒグマ)
早川 慧 / Satoshi Hayakawa
TBA(ニジマス、ホウライマス、模様)
吉野 裕生 / Yuki Yoshino
TBA(湧水)
修士1年
遠藤 岬 / Misaki Endo
TBA
根来 晃佑 / Kosuke Negoro
negoro.kosuke.c2(at)elms.hokudai.ac.jp
イワナの模様
魚が好きで、特にサケ科魚類が大好きです。それらを絵に描くことも好きです。子供のころから昆虫、爬虫類や恐竜、植物など様々な生き物を描いていましたが、いつの頃からかサケ科魚類ばかり描くようになっていました。サケ科魚類は体色のバリエーションが豊富で、どれだけ描いても描き足りません。サケ科魚類の大きな魅力である模様の多型について研究したいので、この研究室に来ました。まずはサケ科魚類の中でもイワナに注目して、模様に関する研究を進めていきます。